肋骨周りが痛いときは何科に行くべき?肋間神経痛の痛みを和らげる方法を徹底解説
- 長沼整形外科・内科医院
- 3月23日
- 読了時間: 17分
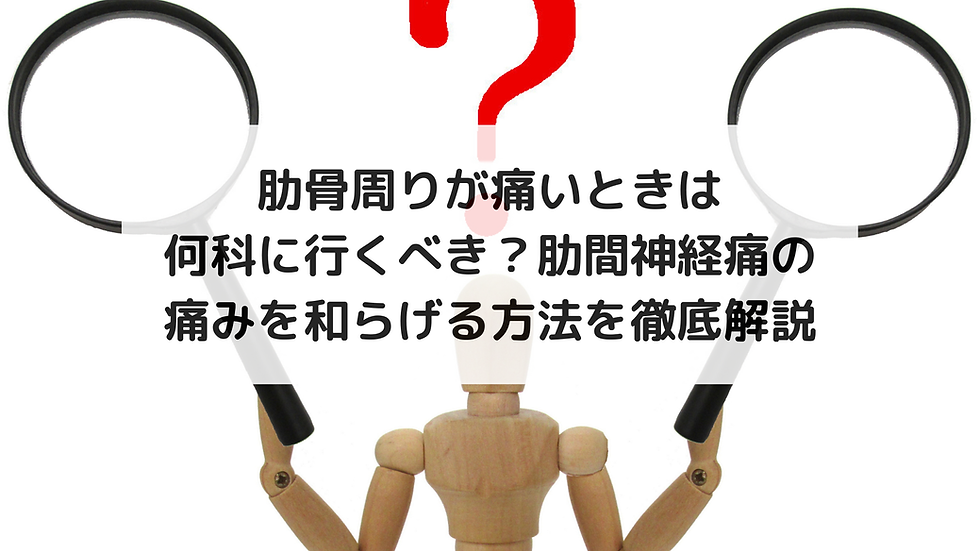
【本記事の要点】
肋間神経痛の症状と原因: 肋骨に沿った痛みで、姿勢の悪さやストレス、帯状疱疹が主な原因。
何科を受診すべきか: 肋間神経痛は整形外科で診察、帯状疱疹は皮膚科、内臓疾患は内科で確認。
肋間神経痛の診断方法: 問診やレントゲン、MRIで原因を特定。
治療と予防法: 鎮痛薬やリハビリ、姿勢改善で痛みを和らげ、再発を防ぐ。
▶︎1. 肋間神経痛とは?何科で診てもらえる?
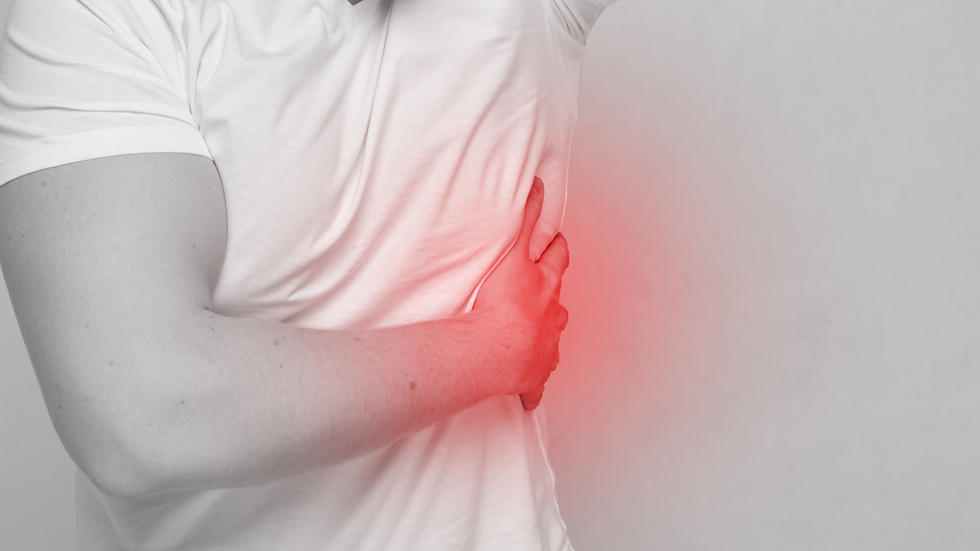
1.1 肋間神経痛の定義と症状
肋間神経痛とは、肋骨に沿って走る「肋間神経」が刺激されることで生じる痛みのことを指します。特に、胸や背中、脇腹に鋭い痛みやズキズキする痛みを感じるのが特徴です。
肋間神経痛の主な症状
鋭い刺すような痛み(電気が走るような感覚)
ズキズキとした鈍い痛みが続くこともある
深呼吸や咳・くしゃみで痛みが増す
体の片側だけに痛みが現れることが多い
一時的な痛みから慢性的な痛みまで幅広い
肋間神経痛は、数秒から数分の短時間で痛みが走るケースもあれば、慢性的に痛みが続くケースもあります。痛みの種類や継続時間によって原因が異なることが多いため、症状の特徴をしっかり把握しておくことが大事です。
また、「心臓の病気と勘違いしやすい」という点も注意が必要です。特に左胸に痛みを感じる場合は、心筋梗塞や狭心症との区別が難しいことがあります。肋間神経痛かどうか判断に迷う場合は、早めに病院を受診するのが安心です。
1.2 肋間神経痛の原因
肋間神経痛の原因はさまざまですが、大きく分けると「外的要因」と「内的要因」に分類できます。それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。
外的要因(体の外からの影響)
姿勢の悪さ:長時間のデスクワークや猫背が原因で、肋間神経が圧迫される
怪我や打撲:転倒やスポーツでの衝撃が肋骨や神経を刺激する
過度な運動やストレッチ:無理な動きで神経を引っ張り、炎症が起こる
長時間の同じ姿勢:特にPC作業やスマホ操作で、筋肉の緊張が神経を圧迫
内的要因(体の内部での影響)
帯状疱疹(ヘルペスウイルス):神経に沿って水ぶくれができ、強い痛みを伴う
肋骨や脊椎の異常:骨折や変形が神経を刺激する
ストレスや疲労:自律神経の乱れが痛みを引き起こすことも
加齢による神経の劣化:特に高齢者では神経が弱まり、痛みを感じやすくなる
特に多いのが、姿勢の悪さとストレスによる神経の圧迫です。最近、長時間のデスクワークやスマホ使用で、20〜40代の方でも肋間神経痛を感じるケースが増えています。
また、「ただの神経痛だろう」と放置してしまうと、帯状疱疹や内臓の病気が隠れていることもあるので注意が必要です。痛みが長引く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
▶︎2. 肋間神経痛の症状と特徴|痛みの種類や違いを解説

2.1 痛みの部位と性質
肋間神経痛の痛みは、肋骨に沿って走る神経が刺激されることで起こります。そのため、痛みが現れる部位や性質には特徴があります。
痛みが現れやすい部位
肋骨の周り(胸・脇腹・背中):特に肋骨の下側に沿って痛みが出やすい
片側だけに痛みが出ることが多い(左右どちらかに偏る)
背中から胸にかけて放散する痛み
例えば、左側の肋骨に痛みがあると「心臓の病気では?」と不安になる人も多いですが、肋間神経痛の場合は「動作や姿勢によって痛みが変化する」という特徴があります。
痛みの性質(どんな痛み?)
肋間神経痛の痛みの感じ方は、人によって異なりますが、以下のような特徴があります。
電気が走るような鋭い痛み(突然ズキッとする)
針で刺されるようなチクチクした痛み
焼けるようなヒリヒリした痛み(帯状疱疹の影響がある場合)
ズキズキとした鈍痛が続くこともある
深呼吸や咳、くしゃみで悪化しやすい
例えば、デスクワーク中にふと姿勢を変えたときに「ズキッ」と痛むことがある場合、神経が圧迫されている可能性が高いです。
一方で、安静にしていてもズキズキと痛む場合は、帯状疱疹や内臓の病気が関係していることも。
2.2 症状の持続時間と頻度
肋間神経痛の痛みは、一瞬で終わるものから長時間続くものまで、さまざまなパターンがあります。 どのような持続時間や頻度で現れるのかを知ることで、自分の症状がどのタイプに当てはまるのかを把握しやすくなります。
持続時間の違い
肋間神経痛の痛みの持続時間は、主に以下のようなタイプに分かれます。
瞬間的な痛み(数秒~数分)
突然「ズキッ」と電気が走るような鋭い痛み
咳やくしゃみ、体をひねる動作で誘発されやすい
しばらくすると痛みがなくなり、再び発生することも
慢性的な痛み(数時間~数日)
ズキズキと鈍い痛みが続く
体勢を変えても痛みがなかなか引かない
帯状疱疹後神経痛などが原因のことも
長期間続く痛み(数週間~数カ月)
何もしなくても違和感がある
じわじわとした鈍痛が続き、ストレスで悪化しやすい
慢性化すると、肋間神経が敏感になり、わずかな刺激でも痛みを感じることがある
痛みの頻度の違い
1日に何回も痛みが走るタイプ → 神経の圧迫が原因の可能性が高い
数日に1回のペースで痛みが出る → 疲労やストレスが関係していることも
常に鈍痛が続くタイプ → 帯状疱疹や肋骨の異常などの可能性
例えば、デスクワーク中に毎日のように「ズキッ」と痛みが走る場合は、長時間の姿勢の悪さが原因かもしれません。 一方で、ずっと鈍い痛みが続く場合は、帯状疱疹後の神経痛や肋骨の問題が関係していることも。
痛みの持続時間や頻度をチェックすることで、原因を推測しやすくなります。
2.3 他の疾患との鑑別ポイント
肋間神経痛は、他の病気と症状が似ているため、自己判断が難しいことがあります。特に、心臓や肺、胃の病気と間違えやすいため、違いを知っておくことが大切です。
1. 心臓の病気(狭心症・心筋梗塞)との違い
項目 | 肋間神経痛 | 狭心症・心筋梗塞 |
痛みの性質 | 刺すような痛み、電気が走るような鋭い痛み | 締めつけられるような圧迫感のある痛み |
痛みの部位 | 肋骨に沿った痛み(片側が多い) | 胸の中央や左胸に広がる痛み |
痛みの持続時間 | 数秒〜数分、動作によって変化 | 数分〜20分以上続くことも |
誘発される動作 | 咳、くしゃみ、深呼吸、姿勢の変化で悪化 | 運動時やストレスを感じたときに発生 |
その他の症状 | 特になし | 冷や汗、吐き気、めまいを伴うことが多い |
左胸に痛みを感じた場合でも、姿勢や動作で痛みが変化するなら肋間神経痛の可能性が高いです。一方で、胸全体が締めつけられるような痛みが続き、冷や汗や吐き気を伴うなら、心臓の病気を疑いましょう。
2. 肺の病気(肺炎・気胸)との違い
項目 | 肋間神経痛 | 肺の病気(肺炎・気胸) |
痛みの性質 | チクチク、ズキズキする痛み | 呼吸時に強くなる痛み |
痛みの部位 | 肋骨に沿った部分 | 胸の奥の方、または片側の肺の周辺 |
呼吸への影響 | 深呼吸や咳で悪化することがある | 息苦しさ、呼吸困難を伴うことが多い |
発熱の有無 | なし | 肺炎の場合、発熱や咳が出ることがある |
息苦しさが強い場合や発熱がある場合は、肺の病気の可能性も考えられます。特に、突然の息切れを感じるなら気胸の疑いがあるため、早めに受診しましょう。
3. 胃の病気(胃潰瘍・逆流性食道炎)との違い
項目 | 肋間神経痛 | 胃の病気(胃潰瘍・逆流性食道炎) |
痛みの性質 | 鋭い痛みやズキズキした痛み | 胸やみぞおちが焼けるような痛み |
痛みの部位 | 肋骨に沿った部分(脇腹や背中も含む) | みぞおちや胸の中央 |
食事との関係 | 特になし | 食後に悪化することが多い |
その他の症状 | なし | 胸焼け、げっぷ、酸っぱいものがこみ上げる |
みぞおちのあたりに痛みを感じ、食後に悪化する場合は、胃の病気の可能性が高いです。
受診の目安
姿勢を変えたり、動くと痛みが増す → 肋間神経痛の可能性が高い
安静時でも痛みが続く・締めつけられるような痛み → 心臓の病気を疑う
息苦しさがある・咳や発熱を伴う → 肺の病気の可能性
食後に痛みが悪化する・胸焼けがある → 胃の病気の疑い
自己判断が難しい場合は、できるだけ早めに病院を受診することをおすすめします。
▶︎3. 肋骨周りが痛いときは何科を受診すべき?

3.1 症状や原因別の適切な診療科
肋間神経痛を感じたとき、「何科に行けばいいの?」と迷う方は多いですよね。実は、症状や原因によって適切な診療科が異なります。 受診の目安を詳しく見ていきましょう。
肋間神経痛が疑われる場合の診療科
症状・原因 | 適切な診療科 | 主な検査・治療 |
肋骨に沿った鋭い痛み、深呼吸やくしゃみで悪化 | 整形外科 | レントゲン、MRI、鎮痛薬、リハビリ |
姿勢や動作で痛みが変化する、長時間のデスクワーク | 整形外科・ペインクリニック | 姿勢矯正、ストレッチ指導、ブロック注射 |
帯状疱疹の疑い(赤い発疹や水ぶくれ) | 皮膚科 | 抗ウイルス薬、鎮痛薬 |
みぞおち周辺の痛み、食後に悪化 | 消化器内科 | 胃カメラ、ピロリ菌検査 |
息苦しさや発熱、咳が続く | 呼吸器内科 | 胸部レントゲン、CT、血液検査 |
胸の圧迫感や冷や汗、動悸 | 循環器内科 | 心電図、心エコー、血液検査 |
まずは整形外科が基本!ただし例外もある
肋間神経痛の多くは、神経や筋肉の問題が関係しているため、まずは「整形外科」を受診するのが一般的です。特に、姿勢の悪さや筋肉のこりが原因の場合は、整形外科で適切な治療を受けられます。
しかし、痛みの原因が「帯状疱疹」や「内臓の病気」にある場合は、整形外科ではなく皮膚科や内科の受診が必要になることも。
「いつもの神経痛と違う」「痛みの原因がはっきりしない」場合は、早めに専門の診療科を受診しましょう。
3.2 初診時の診療科の選び方
肋間神経痛のような症状を感じたとき、「どの診療科に行けばいいの?」と迷うことがありますよね。特に、痛みの原因がわからない場合は、適切な診療科を選ぶのが難しくなります。そこで、初診時にどの診療科を受診すべきか、選び方のポイントを解説します。
まずは整形外科が基本
肋間神経痛の多くは、肋骨や神経、筋肉に関連した痛みのため、まずは「整形外科」を受診するのが一般的です。
こんな症状があるなら整形外科へ
肋骨に沿った痛みがあり、特に動作や姿勢の変化で悪化する
デスクワークや長時間の同じ姿勢で痛みが増す
背中や脇腹の筋肉が張っている感じがする
整形外科では、レントゲンやMRI検査を行い、骨や神経の異常がないかをチェックします。筋肉の緊張が原因の場合は、ストレッチやリハビリ、痛み止めの処方などの治療を受けることができます。
症状別の診療科の選び方
整形外科以外にも、症状によって適切な診療科が異なります。 以下のポイントを参考にしてください。
発疹や水ぶくれがある場合 → 皮膚科(帯状疱疹の可能性)
胸の圧迫感や冷や汗、動悸がある場合 → 循環器内科(心臓の病気の可能性)
息苦しさや長引く咳、発熱がある場合 → 呼吸器内科(肺の病気の可能性)
みぞおちの痛みや食後の違和感がある場合 → 消化器内科(胃の病気の可能性)
迷ったら「内科」へ行くのも選択肢
「どの診療科に行けばいいかわからない…」という場合は、内科を受診するのも一つの方法です。内科では、診察や基本的な検査を行い、必要に応じて適切な診療科を紹介してくれます。
特に、痛みの原因がわからず不安な場合は、内科で相談するのが安心です。
3.3 診療科ごとの対応内容
肋間神経痛の症状で病院を受診すると、診療科ごとに異なる検査や治療が行われます。どの診療科で何をしてもらえるのかを知っておくと、スムーズに診察を受けられます。
1. 整形外科(神経や筋肉の異常をチェック)
主な検査・診断
レントゲン(骨折や異常の有無を確認)
MRI(神経の圧迫やヘルニアの可能性を調べる)
触診(姿勢や筋肉のこりをチェック)
主な治療方法
痛み止めの処方(飲み薬・湿布・塗り薬)
ブロック注射(強い痛みを抑える)
ストレッチやリハビリ指導
肋間神経痛の多くは、まず整形外科で診察を受けるのが基本です。
2. 皮膚科(帯状疱疹の疑いがある場合)
主な検査・診断
皮膚の視診(水ぶくれや赤い発疹の確認)
血液検査(ウイルスの有無を調べることも)
主な治療方法
抗ウイルス薬の処方(帯状疱疹の進行を抑える)
痛み止めの処方(神経痛を抑える)
発疹やピリピリした痛みがある場合は、皮膚科で早めに診てもらいましょう。
3. 循環器内科(心臓の病気が疑われる場合)
主な検査・診断
心電図(不整脈や狭心症の有無を確認)
血液検査(心臓のダメージを調べる)
心エコー(心臓の動きをチェック)
主な治療方法
心臓病が疑われる場合は、専門的な治療を実施
高血圧やコレステロールの管理
胸の圧迫感や冷や汗を伴う痛みがある場合は、すぐに循環器内科を受診しましょう。
4. 呼吸器内科(肺の病気が疑われる場合)
主な検査・診断
胸部レントゲン(肺の状態を確認)
CTスキャン(より詳しい画像検査)
血液検査(炎症の有無を調べる)
主な治療方法
肺炎や気胸の場合は、投薬や酸素療法を実施
喘息が原因の場合は、吸入薬を処方
咳が長引く、息苦しさがある場合は、呼吸器内科の受診がおすすめです。
5. 消化器内科(胃や食道の病気が疑われる場合)
主な検査・診断
胃カメラ(胃や食道の炎症を確認)
ピロリ菌検査(胃のトラブルの原因を調査)
超音波検査(内臓の異常をチェック)
主な治療方法
胃酸を抑える薬の処方
食生活の改善指導
食後に痛みが悪化する場合や胸焼けがある場合は、消化器内科で相談しましょう。
受診する診療科の選び方
肋骨に沿った痛みや姿勢によって変化する痛み → 整形外科
発疹やピリピリした痛みがある → 皮膚科
胸の圧迫感や冷や汗を伴う痛み → 循環器内科
咳が長引く、息苦しさがある → 呼吸器内科
食後に痛みが悪化する、胸焼けがある → 消化器内科
どの診療科に行くか迷った場合は、まず内科を受診するのも選択肢の一つです。内科では、診察をした上で、必要に応じて適切な診療科へ案内してもらえます。
▶︎4. 肋間神経痛の診断と治療法|どんな検査や治療をする?
4.1 診断の流れと主な検査
肋間神経痛の診断では、問診・視診・画像検査を行い、痛みの原因を特定します。
診断の流れ
問診(症状の詳細、痛みの頻度・持続時間、既往歴などを確認)
視診・触診(姿勢や筋肉の緊張をチェック)
画像検査(必要に応じてレントゲン・MRI・CTを実施)
主な検査方法
レントゲン:骨折や骨の異常を確認
MRI:神経の圧迫やヘルニアを詳細に調べる
CTスキャン:肺や内臓の異常がないかを確認
心電図・血液検査:心疾患や炎症の有無をチェック(必要時)
肋間神経痛の診断は整形外科が基本ですが、症状によっては他の診療科で追加検査を行うこともあります。
4.2 薬物療法とその効果
肋間神経痛の治療では、痛みを和らげる薬を使用するのが一般的です。症状の程度に応じて、内服薬や外用薬が処方されます。
主な薬の種類と効果
鎮痛剤(NSAIDs):ロキソプロフェンやイブプロフェンなど、炎症を抑え痛みを軽減
筋弛緩剤:筋肉の緊張をほぐし、神経の圧迫を和らげる
神経障害性疼痛治療薬:神経の過敏な反応を抑え、慢性的な痛みに効果的
ビタミンB12(メコバラミン):神経の修復を促進し、長引く痛みに有効
湿布・塗り薬:炎症を抑え、局所的に痛みを和らげる
症状が軽度なら鎮痛剤や湿布で対応できますが、痛みが強い場合は神経ブロック注射などの処置が検討されます。
4.3 リハビリテーションや物理療法
肋間神経痛の治療では、リハビリや物理療法を取り入れることで、痛みの軽減や再発予防が期待できます。
主なリハビリ・物理療法
ストレッチ:肋間の筋肉を伸ばし、神経の圧迫を軽減
温熱療法:ホットパックや温湿布で血流を促進し、痛みを和らげる
低周波治療:電気刺激を与え、筋肉の緊張をほぐす
姿勢改善トレーニング:猫背や反り腰を修正し、神経への負担を減らす
軽い運動(ウォーキング・ヨガ):血流を良くし、筋肉の硬直を防ぐ
薬物療法だけでなく、リハビリや物理療法を並行して行うことで、より早く痛みを和らげることができます。
4.4 日常生活での注意点とセルフケア
肋間神経痛の症状を和らげ、再発を防ぐためには、日常生活での工夫が重要です。
生活習慣の見直し
長時間同じ姿勢を避ける:デスクワーク中は1時間に1回ストレッチをする
適度な運動を取り入れる:軽いストレッチやウォーキングで血流を促進
体を冷やさない:寒さで筋肉が硬直しやすいため、温める習慣をつける
寝る姿勢を見直す:硬すぎるマットレスや高すぎる枕は避ける
痛みがあるときのセルフケア
温める or 冷やす:急な痛みには冷やし、慢性的な痛みには温める
深呼吸を意識する:呼吸を浅くしないようにし、リラックスする
痛みが強いときは無理をしない:症状が長引く場合は早めに医療機関を受診
日常生活の工夫次第で、肋間神経痛の痛みを軽減し、再発を防ぐことができます。
▶︎5. 肋間神経痛の予防と再発防止策|自分でできる対策
5.1 生活習慣の見直し
肋間神経痛の予防には、日常の姿勢や生活習慣を改善することが大切です。特に、デスクワークが多い人や運動不足の人は注意が必要です。
見直すべき生活習慣
長時間同じ姿勢を続けない:1時間ごとに軽く体を動かす
適度な運動を習慣にする:ストレッチや軽い筋トレで筋肉を柔軟に保つ
正しい姿勢を意識する:猫背や反り腰を防ぎ、背筋を伸ばす
体を冷やさない:冬場はカイロや温熱シートを活用し、血行を良くする
十分な睡眠をとる:疲労回復を促し、神経への負担を減らす
普段のちょっとした習慣を変えるだけで、肋間神経痛のリスクを減らすことができます。
5.2 ストレス管理とリラクゼーション
ストレスは肋間神経痛を悪化させる原因の一つです。自律神経の乱れや筋肉の緊張を防ぐために、適切なストレス管理が大切です。
ストレスを和らげる方法
深呼吸や瞑想を取り入れる:1日5分の深呼吸でリラックス
趣味の時間を確保する:好きな音楽や読書で気分転換
十分な睡眠をとる:寝不足は痛みを悪化させるため、睡眠環境を整える
温浴やマッサージを活用する:38〜40℃のぬるめのお湯に浸かると副交感神経が優位に
仕事や家事の合間にストレッチをする:肩や背中の緊張をほぐす
ストレスを減らすことで、肋間神経痛の予防だけでなく、心身の健康も改善できます。
5.3 適切な運動と姿勢の維持
正しい姿勢と適度な運動を習慣化することで、肋間神経痛の予防と改善が期待できます。
おすすめの運動
軽いストレッチ:胸や背中を伸ばし、神経の圧迫を防ぐ
ウォーキング:血流を促進し、筋肉のこりを軽減
ヨガやピラティス:体幹を鍛え、姿勢を整える
軽い筋トレ:腹筋や背筋を鍛えて姿勢をサポート
正しい姿勢のポイント
座るときは背筋を伸ばし、深く腰掛ける
PC作業時は画面の高さを目線と合わせる
長時間同じ姿勢を続けず、こまめに動く
運動と姿勢の改善を意識することで、肋間神経痛のリスクを大幅に減らせます。
▶︎6. まとめ
肋間神経痛は、肋骨に沿って走る神経が刺激されることで起こる鋭い痛みが特徴です。深呼吸やくしゃみ、姿勢の変化によって痛みが悪化することがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。原因はさまざまで、姿勢の悪さやストレス、帯状疱疹、肋骨の異常などが関係していることが多いため、適切な診療科を受診することが大切です。
肋間神経痛のポイントまとめ
主な症状:肋骨に沿った痛み、ピリピリ・ズキズキとした痛み、深呼吸や咳で悪化することも
受診すべき診療科:基本は整形外科。帯状疱疹が疑われる場合は皮膚科、内臓の異常が考えられる場合は内科や循環器内科も検討
診断方法:問診や視診、レントゲン・MRI・CTなどの画像検査を用いて原因を特定
治療法:鎮痛剤や筋弛緩剤の処方、神経ブロック注射、ストレッチや温熱療法などのリハビリを組み合わせる
予防策:正しい姿勢を意識し、ストレッチや適度な運動を取り入れて神経への負担を減らす
日常生活の中で、長時間の同じ姿勢やストレスが痛みを悪化させる要因となるため、生活習慣の見直しも重要です。デスクワークが多い人は1時間に1回は体を動かし、血流を良くする習慣をつけるのがおすすめです。また、冷えは神経痛を悪化させることがあるため、冬場は体を温める工夫をすることで痛みの軽減につながります。
肋間神経痛は適切な診療とセルフケアによって改善が可能なため、無理をせず早めに医療機関を受診し、自分に合った治療を受けることが大切です。痛みが続く場合は放置せず、専門医に相談しましょう。
▶︎肋骨周りの診察なら、永沼整形外科へご相談を!
肋骨まわりの痛みや違和感でお悩みではありませんか?永沼整形外科では、肋間神経痛の診断・治療を丁寧に行い、患者様の症状に合わせた最適なケアをご提供します。
専門医による診察を受けたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
Comments