リハビリではどんなことをするの?種類や流れを徹底解説!
- 長沼整形外科・内科医院
- 3月23日
- 読了時間: 17分
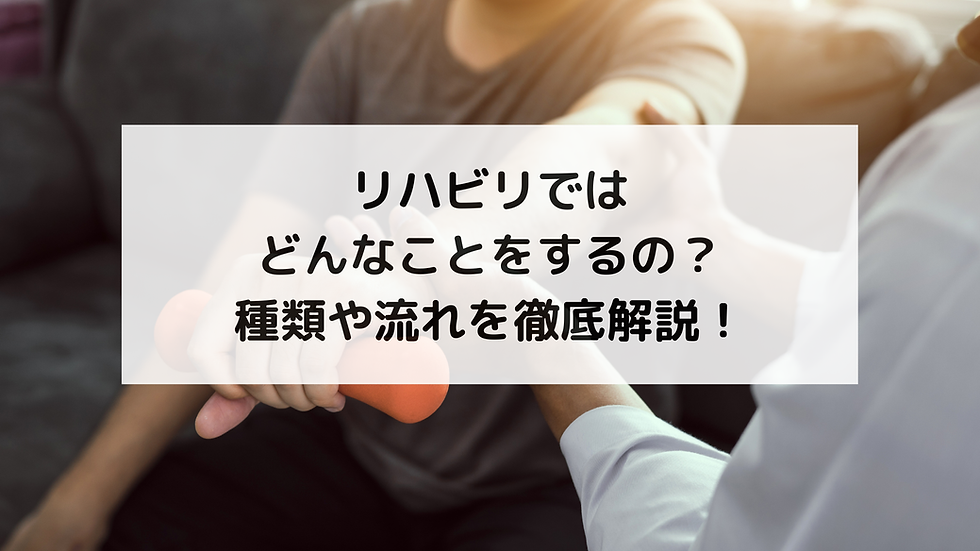
【本記事の要点】
リハビリの種類と目的:理学療法や作業療法など、体の機能回復や生活の質向上を目指す。
リハビリの流れと進め方:急性期から維持期まで、段階ごとにトレーニングを行う。
自宅でできるリハビリ:簡単な運動や動作訓練を自宅で続けることが回復をサポート。
リハビリの効果を高める方法:継続と目標設定、家族のサポートで効果が高まる。
▶︎1. リハビリテーションとは?どんなことをするの?

1.1 リハビリテーションの定義と目的
リハビリテーションとは、病気やケガで失われた身体機能や生活能力を回復し、日常生活へ復帰できるよう支援するプロセスのことです。「リハビリ=運動療法」と思われがちですが、実際には社会復帰や精神的サポートも含まれる広い概念なんですよ。
リハビリテーションの語源と基本概念
リハビリテーション(Rehabilitation)の語源は、ラテン語の「rehabilitare(再び適した状態にする)」に由来しています。この言葉には「回復」や「再適応」といった意味があり、単なる身体機能の向上だけでなく、患者さんが以前の生活に近い形で社会復帰できることを目標としています。
リハビリテーションの主な目的
リハビリの目的は、単に動けるようにすることだけではなく、以下のような点を目指します。
身体機能の回復:ケガや病気で低下した筋力や関節の可動域を取り戻す。
生活能力の向上:日常生活動作(ADL)の改善を図り、自立した生活を支援する。
精神的なサポート:回復過程での不安やストレスを軽減し、モチベーションを維持する。
社会復帰の促進:仕事や趣味などの活動に戻るためのサポートを行う。
例えば、脳卒中で半身麻痺になった方がリハビリを通じて歩行能力を取り戻し、最終的に社会復帰を果たすことも少なくありません。リハビリは、単なる治療ではなく、患者さんの「生活の質(QOL)」を向上させるための重要なプロセスなんです。
1.2 リハビリテーションの重要性
リハビリテーションは、単なる機能回復のためだけではなく、患者さんの生活全体に影響を与える重要なプロセスです。リハビリを適切に行うことで、日常生活の質(QOL)を向上させ、心身ともに健康な状態を目指せます。
身体機能の回復と維持
リハビリの最大の目的は、病気やケガによって低下した身体機能を回復し、維持することです。例えば、骨折後に適切なリハビリを行わないと、筋力が低下し、関節の可動域が狭まってしまうことがあります。リハビリを行うことで、これらの問題を防ぎ、スムーズな回復をサポートできます。
自立した生活の確立
リハビリは、日常生活動作(ADL)の向上にも大きく貢献します。歩行、食事、着替え、入浴など、基本的な動作ができるようになることで、介護の必要が減り、より自立した生活を送れるようになります。特に高齢者の場合、リハビリを継続することで「寝たきり」を防ぐ効果も期待できます。
精神的な健康の維持
病気やケガによって身体機能が低下すると、気持ちが沈みがちになります。しかし、リハビリを通じて少しずつ改善を実感することで、自信を取り戻し、前向きな気持ちになれるんです。例えば、脳卒中後のリハビリで「昨日よりも少し指が動いた!」と感じることで、患者さんのモチベーションが大きく向上します。
社会復帰のサポート
リハビリは、仕事や趣味などの活動に復帰するための重要なステップです。例えば、手の麻痺がある方がリハビリを続けた結果、パソコンの操作ができるようになり、職場復帰を果たしたケースもあります。社会とのつながりを維持することは、心の健康にも良い影響を与えます。
リハビリを適切に行うことで、単に「動けるようになる」だけでなく、より充実した人生を取り戻せるんです。
▶︎2. リハビリの種類と特徴

2.1 理学療法ではどんなことをするの?
理学療法(Physical Therapy)は、身体の動きを改善し、筋力や関節の柔軟性を向上させるためのリハビリ方法です。病気やケガで低下した身体機能を回復させ、日常生活の動作をスムーズに行えるようにすることが目的なんですよ。
理学療法の対象となる人
理学療法は、以下のような方に実施されます。
骨折や関節のケガをした人:ギプスが外れた後の筋力低下を防ぐため。
脳卒中後のリハビリが必要な人:麻痺した手足の動きを取り戻すため。
手術後の回復期にある人:人工関節置換術後などの機能回復を促すため。
慢性的な腰痛や膝痛を抱える人:痛みを軽減し、正しい動作を身につけるため。
具体的なリハビリ内容
理学療法では、患者さんの症状に合わせてさまざまな方法が使われます。
運動療法:ストレッチや筋力トレーニングで、動作の改善を図る。
歩行訓練:杖や歩行器を使いながら、安定して歩けるように練習する。
バランストレーニング:転倒を防ぐために、体幹や下半身の筋力を強化する。
関節可動域訓練(ROM訓練):関節の動きを広げ、固まるのを防ぐ。
例えば、脳卒中後の患者さんが、歩行訓練を続けることで「杖なしで歩けるようになった!」というケースも珍しくありません。継続的なリハビリで、日常生活の動作がスムーズになるんです。
2.2 作業療法の内容と目的
作業療法(Occupational Therapy)は、日常生活に必要な動作をスムーズに行えるように支援するリハビリです。単なる身体機能の回復だけでなく、食事や着替え、仕事など「生活の質(QOL)」を向上させることが大きな目的なんですよ。
作業療法の対象となる人
作業療法は、以下のような方に実施されます。
脳卒中や脳損傷の後遺症がある人:麻痺した手を使いやすくするため。
関節リウマチなどで指が動きにくい人:日常生活の動作をスムーズにするため。
高齢で身体機能が低下している人:認知症予防や生活能力向上のため。
精神疾患がある人:社会復帰を目指し、対人スキルを向上させるため。
具体的なリハビリ内容
作業療法では、以下のような方法が用いられます。
日常生活動作訓練(ADL訓練):食事、トイレ、着替えなど、生活に必要な動作を練習する。
手先の機能訓練:ボールをつかむ、ペンで文字を書くなど、指先の動きを鍛える。
道具を使った訓練:ボタンを留める、箸を使うなど、細かい作業の練習をする。
職業復帰のサポート:パソコン操作や作業台を使ったリハビリで仕事復帰を目指す。
例えば、脳卒中で右手が麻痺した方が、作業療法で左手を使った食事や書字の訓練を続けた結果、「左手でもスムーズに食事ができるようになった!」というケースもあります。作業療法は、日常生活をより快適にするための重要なサポートなんです。
2.3 言語聴覚療法とは?
言語聴覚療法(Speech-Language Therapy)は、話す・聞く・食べるといった機能の回復を目的としたリハビリです。特に、脳卒中や病気の後遺症で言葉がうまく話せなくなったり、食事の際にむせやすくなったりする方にとって、とても重要なリハビリなんですよ。
言語聴覚療法の対象となる人
言語聴覚療法は、以下のような方に実施されます。
脳卒中や脳損傷で言葉が出にくくなった人(失語症)
発音が不明瞭になった人(構音障害)
飲み込む力が弱くなった人(嚥下障害)
認知症による会話や記憶の問題がある人
具体的なリハビリ内容
言語聴覚療法では、患者さんの症状に合わせて以下のようなトレーニングを行います。
発声練習:口の動きを鍛えて、はっきりと発音できるようにする。
言葉の理解訓練:簡単な会話や文字の読み書きを練習する。
飲み込みの訓練(嚥下訓練):安全に食事ができるように、舌や喉の動きを改善する。
呼吸訓練:声が出しやすくなるように、発声と呼吸を調整する。
例えば、脳卒中後に「言葉がうまく出てこない」と悩んでいた方が、言語聴覚療法で練習を重ねた結果、「ゆっくりなら会話ができるようになった!」というケースもあります。言語聴覚療法は、コミュニケーションや食事の楽しみを取り戻すための大切なサポートなんです。
▶︎3. リハビリの流れと進め方

3.1 急性期のリハビリテーション
急性期のリハビリテーションとは、病気やケガの発症・受傷直後から始めるリハビリのことです。早期にリハビリを開始することで、筋力の低下や関節の拘縮(こうしゅく)を防ぎ、回復を促進する効果が期待できます。
急性期リハビリの目的
急性期のリハビリは、以下のような目的で行われます。
廃用症候群(はいようしょうこうぐん)の予防:長期間動かないことで、筋力低下や関節のこわばりが進むのを防ぐ。
呼吸・循環機能の維持:ベッド上での軽い運動や座位保持により、肺炎や血栓症のリスクを減らす。
早期回復の促進:適度な運動を行うことで、回復をスムーズに進める。
具体的なリハビリ内容
患者さんの状態に応じて、次のようなリハビリを段階的に行います。
ベッド上での運動:手足をゆっくり動かす、軽いストレッチを行う。
座位訓練:ベッドの背もたれを上げて、少しずつ座る時間を増やす。
立ち上がり・歩行訓練:支えが必要な場合は、理学療法士とともに立ち上がる練習をする。
呼吸リハビリ:深呼吸や咳をする練習で、肺機能を維持する。
例えば、脳卒中で入院した患者さんが、発症後すぐに座位訓練を始めたことで、退院後もスムーズに歩けるようになったというケースもあります。急性期リハビリは、回復を早め、合併症を防ぐための重要なステップなんです。
3.2 回復期のリハビリテーション
回復期のリハビリテーションとは、病気やケガの急性期を乗り越え、機能回復を本格的に進める段階のリハビリです。急性期が過ぎると、筋力や運動能力の回復が本格化し、日常生活へ復帰するためのリハビリが必要になります。
回復期リハビリの目的
回復期のリハビリには、以下のような目的があります。
失われた機能の回復:歩行や手の動きなど、日常生活で必要な動作を改善する。
自立した生活のサポート:食事・トイレ・着替えなどの日常生活動作(ADL)を自分でできるようにする。
社会復帰の準備:職場復帰や趣味の再開に向けたトレーニングを行う。
具体的なリハビリ内容
回復期のリハビリでは、患者さんの目標に合わせて、さまざまな訓練を行います。
歩行訓練:平坦な床や階段を使って、バランスを取りながら歩く練習をする。
筋力トレーニング:下肢や体幹の筋肉を強化し、転倒しにくい体を作る。
作業療法:手や指を使った動作訓練(箸を使う、ボタンを留めるなど)を行う。
言語・嚥下訓練:会話や食事のトレーニングを行い、コミュニケーションや食事の安全性を高める。
例えば、脳卒中で右半身が麻痺した方が、回復期のリハビリで歩行訓練を続けた結果、杖を使って歩けるようになったというケースもあります。回復期リハビリは、社会復帰に向けての大切なステップなんです。
3.3 維持期のリハビリテーション
維持期のリハビリテーションとは、機能回復後の状態を維持し、再発や機能低下を防ぐためのリハビリです。病気やケガの回復が進んだあとも、何もしないと徐々に筋力や動作能力が低下してしまうことがあります。そのため、継続的なリハビリが必要なんですよ。
維持期リハビリの目的
維持期リハビリでは、以下のような目的でトレーニングを行います。
回復した機能を維持する:筋力や柔軟性を維持し、日常生活をスムーズに過ごせるようにする。
再発や機能低下を防ぐ:脳卒中や骨折の再発リスクを下げるために、適度な運動を続ける。
生活の質(QOL)の向上:趣味や仕事を続けるためのサポートを行う。
具体的なリハビリ内容
維持期のリハビリでは、病院だけでなく、自宅や介護施設などで継続できるプログラムを取り入れます。
自宅での運動療法:スクワットやストレッチなど、無理のない範囲で筋力を維持する。
ウォーキングや軽い運動:転倒を防ぐために、散歩や体操を習慣化する。
デイケアや訪問リハビリ:専門家の指導のもと、自分に合ったリハビリを続ける。
認知機能の維持訓練:脳トレや会話を積極的に行い、認知症予防にもつなげる。
例えば、高齢の方が維持期リハビリとして毎日30分のウォーキングを続けたことで、転倒せずに生活できるようになったというケースもあります。維持期リハビリは、長く元気に暮らすための大切な習慣なんです。
▶︎4. リハビリではどんなことをする?具体的な内容
4.1 運動療法の種類と効果
運動療法とは、筋力や関節の動きを改善し、日常生活をより快適にするためのリハビリ方法です。理学療法の一部として取り入れられることが多く、症状や目的に応じたトレーニングを行います。
運動療法の目的
運動療法には、次のような目的があります。
筋力を強化する:筋肉の衰えを防ぎ、動作をスムーズにする。
関節の柔軟性を高める:関節の可動域を広げ、こわばりを防ぐ。
バランス能力を向上させる:転倒予防や歩行の安定につなげる。
痛みを軽減する:適度な運動で血流を促し、慢性的な痛みを和らげる。
具体的な運動療法の種類
運動療法には、大きく分けて以下のような種類があります。
ストレッチ:関節の動きを柔らかくし、筋肉の緊張をほぐす。
筋力トレーニング:スクワットや軽いダンベル運動で、衰えた筋肉を強化する。
歩行訓練:正しい姿勢で歩けるよう、平坦な道や階段を使って練習する。
バランストレーニング:片足立ちや体幹を鍛える運動で、転倒を防ぐ。
例えば、高齢の方が毎日スクワットを10回ずつ続けたことで、歩行が安定し、階段の昇り降りが楽になったというケースもあります。運動療法は、体の機能を高めるだけでなく、生活の自立をサポートする重要なリハビリなんです。
4.2 物理療法で使う機器と施術内容
物理療法とは、電気・温熱・超音波などの物理的な刺激を利用して、痛みを和らげたり、血流を改善したりするリハビリ方法です。運動療法と組み合わせることで、より効果的に回復を促せるんですよ。
物理療法の目的
物理療法は、以下のような目的で行われます。
痛みの軽減:筋肉や関節の痛みを和らげる。
血流の改善:血液の循環を促し、回復を早める。
筋肉の緊張をほぐす:こわばった筋肉をリラックスさせ、動きをスムーズにする。
炎症を抑える:ケガや手術後の腫れや痛みを軽減する。
具体的な施術内容と使用機器
物理療法には、次のような方法があります。
温熱療法:ホットパックや赤外線を使い、血流を促して筋肉を柔らかくする。
電気治療(低周波・干渉波):電気刺激を筋肉に与え、痛みを軽減しながら筋力を維持する。
超音波療法:高周波の振動を使って、深部の筋肉や関節の炎症を抑える。
寒冷療法(アイシング):冷却パックを用いて炎症や腫れを抑える。
例えば、膝の痛みを抱えていた方が低周波治療を受けながら運動療法を続けた結果、膝の曲げ伸ばしが楽になったというケースもあります。物理療法は、痛みを和らげながら回復をサポートする大切な治療法なんです。
4.3 日常生活動作訓練とは?
日常生活動作訓練(ADL訓練)とは、食事やトイレ、入浴、着替えなどの基本的な生活動作をスムーズに行えるようにするためのリハビリです。病気やケガの影響で日常生活が難しくなった方が、自立した生活を取り戻せるようサポートすることが目的なんですよ。
日常生活動作訓練の目的
ADL訓練では、次のような目標を目指します。
生活の自立を促す:食事やトイレなど、介助なしでできる動作を増やす。
転倒やケガの予防:ベッドや椅子からの立ち上がり動作をスムーズにする。
社会復帰のサポート:仕事や趣味に復帰できるよう動作を改善する。
具体的な訓練内容
日常生活動作訓練では、以下のようなリハビリが行われます。
食事動作訓練:スプーンや箸を使う練習をし、飲み込みやすい姿勢を身につける。
トイレ動作訓練:便座への移動やズボンの上げ下げなどをスムーズに行う練習。
入浴・着替え訓練:衣服の着脱を練習し、ボタンやファスナーを扱う訓練をする。
ベッドや車椅子の移乗訓練:ベッドから立ち上がる、車椅子へ移動する練習を行う。
例えば、脳卒中で片手が不自由になった方がリハビリを通じて片手でも服の着脱ができるようになり、自信を取り戻したというケースもあります。ADL訓練は、単なる動作の改善だけでなく、生活の質(QOL)を高めるための重要なリハビリなんです。
▶︎5. リハビリを効果的に行うためのポイント
5.1 リハビリの効果を高めるためにできること
リハビリの効果を最大限に引き出すためには、継続的な努力と正しい方法の実践が大切です。単にリハビリを受けるだけではなく、日々の習慣や意識を変えることで、回復のスピードが大きく変わりますよ。
リハビリの効果を高めるポイント
リハビリを成功させるために、以下の点を意識するとより効果的です。
リハビリを習慣化する:毎日少しずつでもリハビリを続けることで、身体の機能を維持できる。
焦らずコツコツ取り組む:無理をすると逆効果になることもあるので、自分のペースで行うことが大切。
正しいフォームを意識する:間違った動作でリハビリを続けると、別の部位に負担がかかることがある。
リハビリ以外の時間も意識する:普段の生活の中で「できるだけ自分で動く」ことを意識する。
リハビリのモチベーションを維持するコツ
リハビリを続けることが難しいと感じることもありますよね。そんなときは、次の方法を試してみましょう。
小さな目標を設定する:「今日は10回スクワットをする」「杖を使って5メートル歩く」など、達成しやすい目標を立てる。
リハビリの成果を記録する:日記や動画で進歩を記録すると、成長を実感しやすくなる。
家族や周囲の人に協力してもらう:励ましてくれる人がいると、モチベーションが上がる。
楽しみながら取り組む:音楽を聴きながらストレッチをするなど、楽しみを取り入れる。
例えば、脳卒中で片麻痺になった方が、毎日少しずつ歩行訓練を続けたことで、3カ月後には杖なしで歩けるようになったというケースもあります。リハビリの効果を高めるためには、「継続」と「前向きな姿勢」がとても大切なんです。
5.2 自宅でできるリハビリとは
病院や施設でのリハビリだけでなく、自宅でのリハビリを継続することで、回復をさらに促進できます。自分のペースで無理なく取り組むことで、リハビリの効果を最大限に引き出せるんですよ。
自宅リハビリのメリット
毎日継続しやすい:自分の生活リズムに合わせて実施できる。
リハビリを日常生活に取り入れやすい:料理や掃除の動作をリハビリに活用できる。
自主性が高まり、回復が早くなる:積極的に動くことで、身体機能の維持がしやすい。
自宅でできる簡単なリハビリ方法
自宅で取り組めるリハビリには、以下のようなものがあります。
椅子に座ってのスクワット:ゆっくり立ち上がり、ゆっくり座る動作を繰り返す。
タオルを使った握力トレーニング:タオルを丸めてギュッと握る動作を繰り返す。
段差を使ったステップ運動:足を交互に段差に乗せる動作で、下半身の筋力を鍛える。
発声練習(言語リハビリ):口を大きく開けて「ア・イ・ウ・エ・オ」と発声する。
ペンを使った指のトレーニング:指でペンをつまんで移動させ、細かい動作の練習をする。
自宅リハビリを続けるためのポイント
毎日決まった時間に行う:習慣化すると続けやすくなる。
痛みや疲れを感じたら無理をしない:無理せず、自分のペースで取り組む。
家族と一緒に行う:周囲の人と一緒に行うことで、楽しみながら継続できる。
例えば、高齢の方が毎朝10分のスクワットを続けたことで、転倒のリスクが減り、外出が楽しくなったというケースもあります。自宅リハビリは、生活の一部として無理なく続けることが大切なんです。
▶︎6. まとめ:リハビリを効果的に進めるために
リハビリは、単なる運動や治療ではなく、より良い生活を取り戻すための大切なプロセスです。病気やケガの回復をサポートするだけでなく、心身の健康を維持し、日常生活の質(QOL)を向上させることが目的なんですよ。
リハビリのポイントを振り返り
リハビリには段階がある(急性期・回復期・維持期)
理学療法・作業療法・言語聴覚療法など、目的に応じたリハビリがある
運動療法・物理療法・日常生活動作訓練を組み合わせると効果的
リハビリの効果を高めるには、継続とモチベーションが大切
自宅でできるリハビリを取り入れることで、さらに回復が促進される
リハビリを成功させるために大切なこと
焦らず自分のペースで進めること
小さな目標を設定し、達成感を得ること
家族や周囲のサポートを活用すること
無理をせず、楽しみながら続けること
例えば、脳卒中後に毎日少しずつリハビリを続けた方が、半年後には自力で歩けるようになり、以前の生活を取り戻せたというケースもあります。リハビリは続けることで確実に効果が出るものなんです。
無理をせず、楽しみながら取り組むことが、リハビリ成功のカギですよ。あなたやご家族に合ったリハビリ方法を見つけて、より快適な生活を目指しましょう!
▶︎リハビリなら、永沼整形外科にお任せください
リハビリを効果的に進めるには、専門的なサポートが欠かせません。永沼整形外科では、一人ひとりの症状や目標に合わせたリハビリを提供しています。経験豊富なスタッフが丁寧にサポートし、最適なリハビリプランを提案します。
安心して通える環境で、あなたに合ったリハビリを始めてみませんか?
Comments