肋間神経痛の初期症状とは?原因と治療法を解説
- 長沼整形外科・内科医院
- 2月24日
- 読了時間: 18分
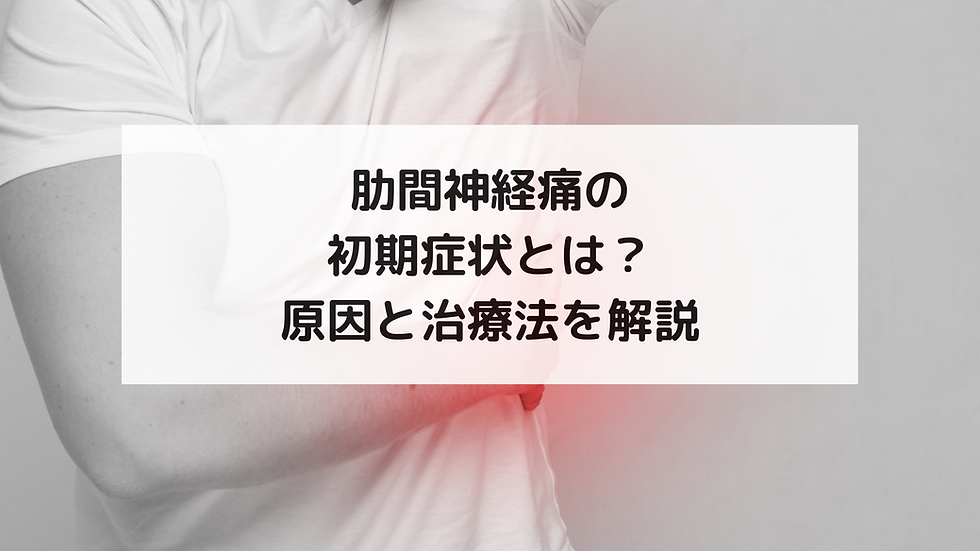
【本記事の要点】
肋間神経痛の概要: 肋間神経の圧迫や炎症で胸や脇腹に痛みが生じ、姿勢や咳で悪化する。
主な原因: 姿勢の乱れ、筋緊張、ストレス、帯状疱疹、肋骨の怪我などが神経を刺激する。
診断と検査: 問診やレントゲン・MRIで骨や神経の異常を確認し、原因を特定する。
治療と対策: 鎮痛薬、リハビリ、ストレッチ、温熱療法で痛みを和らげ、姿勢を改善する。
▶︎1. 肋間神経痛とは?

1.1 肋間神経痛の定義と概要
肋間神経痛とは、肋骨に沿って走る神経が刺激や圧迫を受けることで生じる鋭い痛みのことです。この痛みは、胸部や脇腹を中心に現れ、チクチク・ズキズキとした感覚や電気が走るような鋭い痛みを伴うことが多いです。
肋間神経の役割とは?
肋間神経は、脊髄から出て肋骨に沿って広がる末梢神経の一つです。主に 胸部や脇腹の感覚をつかさどる神経 であり、呼吸や体の動きに連動して働いています。
この神経が何らかの原因で圧迫されたり刺激を受けたりすると、神経が過敏になり痛みを感じるようになります。
肋間神経痛の特徴的な痛み
肋間神経痛の痛みには、いくつかの特徴があります。
片側に痛みが出ることが多い(左右どちらか一方)
ズキズキ、チクチク、刺すような痛み
咳やくしゃみ、深呼吸で痛みが悪化する
数秒〜数分の間、突発的に強い痛みが走る
特に 深呼吸や上半身をひねる動作 で痛みが強くなることが多く、日常生活に支障をきたすこともあります。
1.2 肋間神経痛の主な原因
肋間神経痛は、さまざまな原因によって引き起こされます。その中でも特に多いのが、姿勢の乱れや筋肉の緊張、ストレスなどの要因です。
ここでは、肋間神経痛の主な原因を詳しく見ていきましょう。
1. 姿勢の乱れや筋肉の緊張
長時間のデスクワークやスマホの使用により、猫背や前かがみの姿勢が続くと、肋骨周辺の筋肉が緊張しやすくなります。その結果、肋間神経が圧迫されて痛みを引き起こすことがあります。
猫背や前かがみの姿勢が続くと、胸郭が圧迫されやすい
背中や脇腹の筋肉が硬くなり、神経を刺激する
特に 長時間同じ姿勢を取る習慣がある人 は、肋間神経痛になりやすい傾向があります。
2. ストレスや精神的な緊張
ストレスを感じると、体が無意識に緊張し、呼吸が浅くなることがあります。その結果、肋骨周りの筋肉が硬くなり、神経が圧迫されやすくなります。
緊張すると肩や背中の筋肉がこわばる
呼吸が浅くなり、肋間神経が刺激を受けやすい
特に 仕事や日常生活でストレスを抱えている人 は、肋間神経痛のリスクが高まる可能性があります。
3. 帯状疱疹(たいじょうほうしん)
肋間神経痛の原因として意外と多いのが 帯状疱疹 です。帯状疱疹ウイルスが肋間神経に炎症を引き起こし、ピリピリとした痛みを伴います。
皮膚に赤い発疹や水ぶくれができることが多い
痛みが長期間続くことがある
特に 過去に水ぼうそうにかかったことがある人 は、ウイルスが再活性化して帯状疱疹になる可能性があります。
4. 怪我や外傷
交通事故や転倒などで 肋骨を強く打ったり折れたりすると、肋間神経が傷ついて痛みが出ることがあります。
肋骨の骨折やひびが入ると、神経が圧迫される
外傷がなくても、強い衝撃で神経が損傷することがある
特に スポーツや事故の後に痛みが続く場合 は、医師の診察を受けることが重要です。
5. その他の要因
肋間神経痛の原因は、上記以外にもいくつか考えられます。
更年期障害(ホルモンバランスの変化による影響)
内臓の病気(肺や心臓の疾患が関連することも)
手術後の後遺症(肋骨周辺の神経が影響を受けることがある)
原因がはっきりしない場合は、医師の診察を受けることが大切です。
▶︎2. 肋間神経痛の初期症状とは?

2.1 胸や脇腹の痛みの特徴
肋間神経痛の初期症状で最も特徴的なのが、胸や脇腹に生じる鋭い痛みです。この痛みは、筋肉痛や疲労によるものとは異なり、特定の動作や呼吸によって強くなることが多いのが特徴です。
1. 痛みの種類と感じ方
肋間神経痛の痛みには、いくつかのパターンがあります。
ズキズキと脈打つような痛みが断続的に起こることもあれば、チクチクと針で刺すような感覚や、ピリピリとしたしびれるような痛みを感じる場合もあります。また、焼けるように熱い痛みや、電気が走るような鋭い痛みが一瞬で走ることもあります。
このような痛みは 左右どちらか一方に現れることが多く、広範囲に広がることもあります。
2. 痛みが現れる場所
肋間神経痛の痛みは、肋骨に沿って広がります。特に、以下の部位に痛みを感じることが多いです。
胸の片側(特に肋骨に沿った部分)
脇腹や背中側(肋骨の後ろ側まで痛みが広がることも)
みぞおち周辺(胃のあたりが痛むこともある)
特に 胸の痛みがある場合、心臓や胃の病気と間違えやすいことがあるため注意が必要です。
3. 痛みが悪化しやすい動作やタイミング
肋間神経痛の痛みは、特定の動作や状況で強くなることが特徴です。
たとえば、 深呼吸や咳、くしゃみをすると痛みが走る ことがあります。また、 上半身をひねったり、腕を大きく上げたりする動作 でも痛みが悪化しやすいです。
さらに、 長時間同じ姿勢で座っていると痛みが強くなることもあります。特に寒い環境では神経が過敏になり、夜間に痛みが悪化するケースもあるため、冷え対策も大切です。
2.2 痛みの出やすい動作や状況
肋間神経痛の痛みは、特定の動作や状況で強くなることが特徴です。これは、肋間神経が圧迫されたり、刺激を受けたりすることで痛みが引き起こされるためです。
1. 深呼吸や咳、くしゃみをしたとき
呼吸のたびに肋骨が動くため、深呼吸や咳、くしゃみをすると痛みが悪化することがあります。特に 息を大きく吸い込むと、神経が引っ張られて鋭い痛みが走ることが多い です。
2. 上半身をひねる、体を動かすとき
体を左右にひねったり、横を向いたりする動作でも痛みが出やすいです。これは、 肋骨に沿って走る神経が圧迫されたり、筋肉の緊張が強まったりするため です。
3. 腕を上げる、伸ばす動作をしたとき
洗濯物を干したり、物を取るために腕を高く上げたりすると、肋間神経に負担がかかり痛みが出やすくなります。また、 背中を伸ばすような動作 でも神経が引っ張られ、痛みが悪化することがあります。
4. 長時間同じ姿勢でいるとき
デスクワークやスマホを長時間見ていると、猫背になりやすく、肋骨周辺の筋肉が硬くなります。その結果、肋間神経が圧迫され、 座りっぱなしや立ちっぱなしでも痛みが強くなることがあります。
5. 夜間や寒い環境での痛み
夜間になると神経が過敏になり、 じっとしていてもズキズキと痛むことがあります。また、寒い環境では筋肉がこわばりやすく、痛みが増す傾向にあります。
これらの動作や状況で痛みを感じたら、無理をせず早めに休むことが大切です。
2.3 その他の関連症状
肋間神経痛では、胸や脇腹の痛みだけでなく、さまざまな症状が現れることがあります。これは、肋間神経が皮膚や筋肉だけでなく、他の神経ともつながっているためです。
1. 皮膚の違和感やしびれ
肋間神経が圧迫されることで、 皮膚にチクチクした違和感や軽いしびれを感じることがあります。特に、痛みが出ている部分の皮膚が敏感になり、 触るだけでピリッとした刺激を感じることも。
2. 背中や肩のこり
肋間神経痛があると、 無意識に痛みをかばおうとして姿勢が悪くなり、背中や肩がこりやすくなります。特に長時間同じ姿勢を続けると、筋肉の緊張が強まり、痛みが悪化することもあります。
3. 呼吸のしづらさ
肋骨の動きが制限されるため、 深呼吸をすると違和感を感じたり、息苦しさを覚えたりすることがあります。特に 痛みが強いと、無意識に呼吸が浅くなり、全身の緊張につながることも。
4. みぞおちや脇腹の圧迫感
肋間神経はお腹周りにもつながっているため、 みぞおちや脇腹に圧迫感や違和感を感じることがあります。場合によっては、胃の不調と勘違いすることもあるので注意が必要です。
5. ストレスや不安感
肋間神経痛の痛みが続くと、 「この痛みは何かの病気では?」と不安になり、ストレスを感じることがあります。また、ストレスが筋肉の緊張を悪化させ、さらに痛みが強くなるという悪循環に陥ることも。
これらの症状がある場合は、無理をせず医師に相談することが大切です。
▶︎3. 肋間神経痛の原因とリスク要因

3.1 身体的要因(姿勢や筋肉の緊張など)
肋間神経痛の原因として、姿勢の乱れや筋肉の緊張が大きく関係しています。日常の何気ない動作や習慣が、知らず知らずのうちに肋間神経に負担をかけていることもあるのです。
1. 猫背や前かがみの姿勢
長時間のデスクワークやスマホ操作で前かがみの姿勢が続くと、肋骨の周りの筋肉が硬くなり、肋間神経が圧迫されやすくなります。特に、 肩が前に出て背中が丸くなる「巻き肩」 の人は、肋骨が内側に押し込まれやすく、痛みを感じやすい傾向があります。
2. 筋肉の過度な緊張
筋肉が硬くなると、周囲の神経にも負担がかかります。特に、次のような要因で筋肉が過度に緊張すると、肋間神経痛が起こりやすくなります。
長時間同じ姿勢を続ける(デスクワーク、運転など)
無理な動作や急な動き(重い荷物を持つ、激しい運動など)
筋力不足による姿勢の崩れ
筋肉の緊張は、自律神経とも関係しており、 ストレスが続くと筋肉が硬くなりやすく、痛みを引き起こすこともあります。
3. 背骨や肋骨のゆがみ
姿勢が崩れると、背骨や肋骨の位置が正常でなくなり、肋間神経が圧迫されやすくなります。特に、 脊椎のゆがみ(側弯症など)や、肋骨の動きの制限がある場合 は、肋間神経痛のリスクが高まります。
4. 加齢による筋力低下
加齢とともに筋肉が衰えると、姿勢を支える力が弱まり、肋骨周りの筋肉のバランスが崩れやすくなります。その結果、 神経が刺激を受けやすくなり、ちょっとした動作でも痛みが出やすくなります。
姿勢を意識し、筋肉の緊張を和らげることが、肋間神経痛の予防や改善につながります。
3.2 精神的要因(ストレスや疲労など)
肋間神経痛は、ストレスや精神的な疲労が原因で引き起こされることもあります。ストレスが溜まると自律神経が乱れ、筋肉が緊張しやすくなり、神経を刺激して痛みが生じることがあります。
1. ストレスによる自律神経の乱れ
強いストレスを受けると、自律神経のバランスが崩れます。自律神経には 交感神経(興奮)と副交感神経(リラックス) の2つがあり、交感神経が過剰に働くと筋肉がこわばり、肋間神経に影響を及ぼします。
ストレスが続くことで、以下のような変化が起こります。
呼吸が浅くなる → 肋骨周りの筋肉が硬くなる
肩や背中の筋肉が緊張する → 神経を圧迫する
血流が悪くなる → 神経の働きが鈍くなり、痛みを感じやすくなる
そのため、 ストレスを感じると肋間神経痛の症状が悪化することもあります。
2. 精神的な疲労と睡眠不足
疲れが溜まると、筋肉の緊張が強まり、神経の圧迫につながります。また、 睡眠不足が続くと体の回復力が低下し、痛みを感じやすくなる こともあります。
特に、次のような生活習慣があると、肋間神経痛が悪化しやすくなります。
長時間のデスクワークやスマホ操作で姿勢が悪くなる
忙しさや悩みで十分な休息が取れない
夜更かしが続き、睡眠の質が低下する
精神的なストレスや疲労を和らげるためには、適度な運動やリラックスする時間を持つことが大切です。
3. ストレスが原因の痛みを和らげるには?
肋間神経痛の痛みがストレスと関係している場合、以下のような方法で改善できることがあります。
深呼吸や軽いストレッチで筋肉をほぐす
ぬるめのお風呂に浸かり、リラックスする
適度な運動で血流を促す(ウォーキングなど)
趣味や気分転換をして、ストレスを解消する
心と体の緊張をほぐすことが、肋間神経痛の改善につながります。
3.3 その他の要因(感染症や外傷など)
肋間神経痛は、姿勢やストレスだけでなく、感染症や外傷などの要因によって引き起こされることもあります。特に帯状疱疹(たいじょうほうしん)や肋骨の損傷は、肋間神経に直接影響を与えるため注意が必要です。
1. 帯状疱疹による神経の炎症
帯状疱疹は、水ぼうそうの原因となる「水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)」が体内に潜伏し、免疫力が低下したときに再活性化して発症する病気です。このウイルスが肋間神経に影響を与えると、 ピリピリとした強い痛み を感じることがあります。
帯状疱疹による肋間神経痛の特徴:
痛みとともに、赤い発疹や水ぶくれができる
皮膚がピリピリし、軽く触れるだけで強い痛みを感じる
通常は片側の肋骨に沿って症状が現れる
この場合、皮膚症状がなくても 帯状疱疹後神経痛(PHN) として長期間痛みが続くことがあります。ウイルス感染が疑われる場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。
2. 肋骨の骨折や打撲
交通事故やスポーツなどで 肋骨を強く打ったり、骨折したりすると、肋間神経が圧迫されて痛みが生じることがあります。この場合、 痛みが深呼吸や体の動きに伴って悪化し、骨折部分を押すと強く痛むのが特徴 です。
特に 軽いヒビ(不全骨折) ではレントゲンで異常が見つからないこともありますが、 違和感が続く場合は医師の診察を受けることが重要です。
3. 内臓の病気による関連痛
まれに、 心臓や肺、胃の病気が原因で肋間神経痛と似た痛みが起こることがあります。この場合、神経痛とは異なり、 体を動かしても痛みの強さが変わらないことが多い です。
注意すべき症状の例:
心臓の病気(狭心症・心筋梗塞)→ 胸の締めつけ感、息苦しさを伴う
肺の病気(肺炎・気胸など)→ 呼吸困難、発熱、咳を伴う
胃の病気(胃潰瘍・逆流性食道炎など)→ みぞおちの痛み、胃もたれ、吐き気を伴う
通常の肋間神経痛と異なる違和感がある場合は、速やかに医師の診察を受けることが大切です。
▶︎4. 肋間神経痛の診断と検査方法
4.1 医療機関での診察プロセス
肋間神経痛の痛みが続く場合や、日常生活に支障をきたすほど強い場合は、医療機関での診察が必要です。診察では、問診や視診、必要に応じて検査を行い、神経痛の原因を特定していきます。
1. 問診(症状の聞き取り)
まず、医師は 痛みの特徴や発症時期、悪化する動作などを詳しく聞き取ります。特に以下のような質問を受けることが多いです。
痛みは どこに 感じるか(胸・脇腹・背中など)
いつから痛みを感じるようになったか
痛みの 強さや頻度(ズキズキする、刺すような痛み、断続的 or 継続的)
体を動かすと痛みが悪化するか
皮膚の異常(発疹など)があるか
心臓や肺の病気との区別が重要なため、息苦しさや動悸などの症状も確認されることがあります。
2. 視診・触診(体の状態をチェック)
問診の後、 実際に痛みのある部位を確認し、神経や筋肉の状態をチェック します。触診では、 痛みのある肋骨部分を軽く押したときの反応や、筋肉のこわばりの有無 を調べます。
また、 姿勢や背骨のゆがみ なども診察し、痛みの原因を探ります。
3. 必要に応じた検査
肋間神経痛の原因をより詳しく調べるために、以下のような検査が行われることがあります。
レントゲン検査(X線) → 肋骨の骨折や異常の有無を確認
MRI検査 → 神経の圧迫や椎間板の異常を詳しく調べる
血液検査 → 炎症や感染症(帯状疱疹など)の可能性を確認
心電図・胸部CT → 心臓や肺の病気が疑われる場合に実施
検査の結果、他の病気が原因でないかを慎重に見極めます。
4. 診断と治療方針の決定
問診・視診・検査の結果をもとに、 肋間神経痛の診断が確定されると、治療方針が決まります。痛みの程度や原因に応じて、 薬物療法やリハビリ、生活習慣の改善 などの治療が提案されます。
早めに医療機関を受診することで、適切な治療を受け、症状を和らげることができます。
4.2 主な検査方法とその目的
肋間神経痛の診断では、痛みの原因を正確に特定するために、さまざまな検査が行われます。特に、骨や神経、筋肉の異常を調べることが重要です。
1. レントゲン検査(X線)
レントゲン検査では、肋骨の骨折や異常の有無を確認します。肋間神経痛の原因として、骨折や骨の変形が関係していることがあるため、まず最初に行われることが多い検査です。
この検査は短時間で撮影でき、放射線の被ばく量も少ないため、安全に実施できます。ただし、レントゲンでは神経や筋肉の状態は確認できません。
2. MRI検査(磁気共鳴画像検査)
MRIは、神経や筋肉、椎間板などの軟部組織の異常を詳しく調べる検査です。特に、神経の圧迫や炎症が疑われる場合に有効で、レントゲンでは見えない部分の状態を確認できます。
椎間板ヘルニアや背骨の変形が関係している場合、MRI検査によって明らかになることがあります。放射線を使用しないため、安全性が高いのも特徴です。
3. 血液検査
血液検査では、体内の炎症やウイルス感染の有無を調べます。特に、帯状疱疹ウイルスが原因となる「帯状疱疹後神経痛」が疑われる場合、この検査が重要になります。
また、関節リウマチなどの炎症性疾患が関係しているかどうかも血液検査で確認できます。
4. 神経伝導検査
神経伝導検査は、神経の働きを調べるための検査です。電気刺激を与え、神経が正しく信号を伝達しているかを測定します。
肋間神経に障害がある場合、通常よりも信号の伝達が遅くなるため、痛みの原因が神経の損傷によるものかどうかを判断するのに役立ちます。
5. 心電図・胸部CT(必要に応じて)
肋間神経痛の痛みは、心臓や肺の疾患と症状が似ていることがあります。そのため、心電図や胸部CTを用いて、狭心症や心筋梗塞、肺の病気が関係していないかを確認することもあります。
特に、動悸や息苦しさを伴う場合や、痛みが広範囲に及ぶ場合には、これらの検査が必要になることがあります。
検査の流れ
医師は、問診と視診を行った上で、必要な検査を選択します。一般的には、レントゲン検査で骨の異常を確認し、さらに詳しく調べるためにMRIや血液検査が行われます。神経の異常が疑われる場合には、神経伝導検査が追加されることもあります。
痛みの原因を特定することで、適切な治療方針が決まり、早期改善につなげることができます。
▶︎5. 肋間神経痛の治療法と対処法
5.1 薬物療法の種類と効果
肋間神経痛の治療では、痛みを和らげるために薬物療法が用いられます。症状の程度に応じて、以下のような薬が処方されます。
1. 鎮痛薬(痛み止め)
ロキソプロフェンやイブプロフェンなどの 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) は、炎症を抑えて痛みを軽減します。胃に優しい アセトアミノフェン も選択肢の一つです。
2. 神経障害性疼痛治療薬
神経の興奮を抑える プレガバリン(リリカ) や デュロキセチン は、慢性の神経痛に効果があります。
3. 筋弛緩薬とビタミンB12
エペリゾン(ミオナール) は筋肉の緊張を和らげ、メコバラミン(メチコバール) は神経の回復を助けます。
4. 神経ブロック注射
局所麻酔を用いて痛みを一時的に遮断する方法で、強い痛みに効果的です。
薬の選択は、症状や体質に合わせて行われます。長期使用は副作用のリスクがあるため、医師の指示に従いましょう。
5.2 リハビリテーションや理学療法の役割
肋間神経痛の改善には、リハビリテーションや理学療法が有効です。筋肉の緊張をほぐし、神経への負担を減らすことで、痛みの軽減を目指します。
1. 温熱療法
ホットパックや電気治療を用いて 血流を促進し、筋肉のこわばりを和らげる ことで、痛みを軽減します。
2. 低周波治療
微弱な電気刺激を与え、 神経や筋肉のリラックスを促し、痛みを軽減 する治療法です。
3. ストレッチ・運動療法
姿勢の改善や筋力維持のため、 肩回しや胸を開くストレッチ などが推奨されます。
4. 自宅でのケア
日常的に 正しい姿勢を意識し、軽いストレッチや深呼吸を取り入れる ことで、症状の再発を防ぐことができます。
リハビリを継続することで、肋間神経痛の予防と改善が期待できます。
5.3 生活習慣の改善とセルフケア
肋間神経痛を悪化させないためには、日常生活でのセルフケアが重要です。姿勢の見直しや適度な運動を取り入れ、神経への負担を減らしましょう。
1. 姿勢の改善
猫背や前かがみの姿勢は 肋骨周りの神経を圧迫するため、背筋を伸ばす習慣 をつけましょう。長時間同じ姿勢を続けるのも避けることが大切です。
2. 体を冷やさない
冷えは 血流を悪化させ、神経痛を悪化させる原因 になります。カイロや温熱パッドを活用し、肋骨周りを温めましょう。
3. 適度な運動
軽いストレッチやウォーキングは 筋肉の緊張をほぐし、血流を促進する効果 があります。
4. ストレス管理
ストレスは 自律神経を乱し、痛みを悪化させる ことがあるため、深呼吸や趣味でリラックスする時間を作りましょう。
日々のセルフケアを意識することで、肋間神経痛の再発を防ぐことができます。
▶︎6. まとめ:肋間神経痛の初期症状を知り、早めの対策を
肋間神経痛は、初期症状を見逃さず、適切な対策を取ることで悪化を防ぐことができます。特に、胸や脇腹のチクチクした痛みや深呼吸時の違和感が続く場合は、早めの対応が重要です。
1. 初期症状を見逃さない
ズキズキ・ピリピリとした痛みが続く場合、 姿勢の改善やストレッチを取り入れる ことで症状が軽減することがあります。
2. 早期受診の重要性
痛みが続く場合は 整形外科を受診し、適切な治療を受けることが大切 です。薬物療法やリハビリを組み合わせることで、症状の改善が期待できます。
3. 生活習慣の見直し
正しい姿勢を維持し、冷え対策や適度な運動を取り入れることで 再発予防 にもつながります。
肋間神経痛の症状でお悩みの方は、早めに専門医へ相談しましょう。
▶︎肋間神経痛の初期症状でお悩みの方は、永沼整形外科にご相談ください
肋間神経痛は、早めの診察と適切な治療が大切です。「胸や脇腹にチクチクした痛みがある」「深呼吸や体の動きで痛みが悪化する」などの症状が続く場合、放置せずに専門医に相談しましょう。
永沼整形外科では、整形外科の専門医が診察を行い、最新のリハビリ機器を活用した治療を提供しています。痛みの原因を特定し、患者様一人ひとりに合った治療プランをご提案します。
肋間神経痛の症状でお悩みの方は、お気軽に当院までご相談ください。
Comments